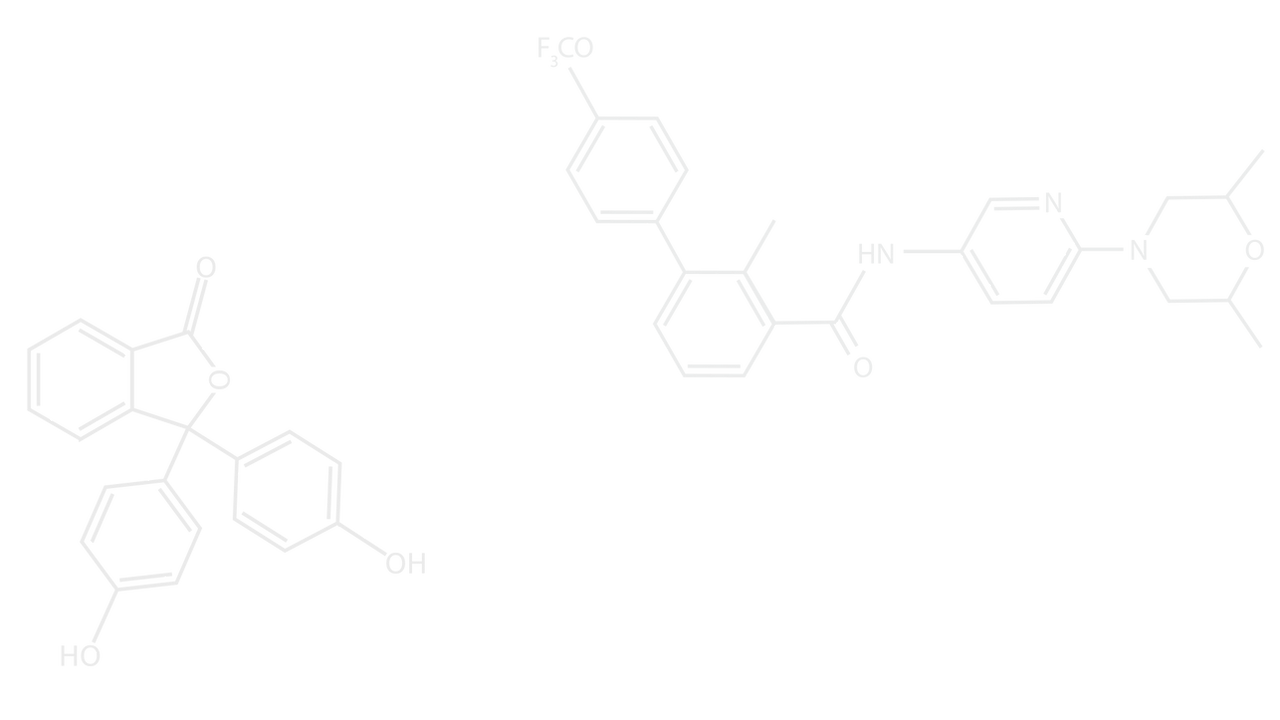
植民地朝鮮の日本人宗教者
記事題目
「朝鮮人布敎に苦心せる巌常圓氏」
作者
京大 竹朗生(投)
雑誌名
『中外日報』
号数等
年月日
1913年11月15・16日
本文
私が此夏滿鮮を旅行して、僧俗種々の人に面會した、皆夫々に種々の敎訓を與へて貰つた、其内最も真摯に私の信仰を導いて下さつた巌常圓氏の事を、皆様に御紹介致し度いと思ひます。
巌氏は現在は京城々外の朝鮮人のみを収監する監獄の敎誨師をして居られますが、氏の如き方が新同胞の間に阿弥陀の福音を伝へらるゝのは實に嬉しく感じましたのです。
種々信仰上の御話を承はつた後、渡韓の動機や布敎の状況波瀾曲折をお尋した。
氏は始め京都で、某西洋人の家より同志社に通學して神學科を卒へたが、其以前より基督敎に疑惑を懐き當時、中學校長をして居た清澤滿之先生の歸途をつけて、悶々の情を述べ、種々指導を受けた同志社を卒業してから、真宗大學に入つて明治參十五年に卒業し、始めは支那へ布敎に行かんと企てたのであつたが、家庭の事情で遂に一年餘を内地に過した鬱勃たるたる英氣は、因襲に囚はれて全く沈滞せる我國の宗敎界にては到底滿足出來ず、偶々呉港にて日本名を北野逸平らといふ朝鮮人に邂逅し、鮮人の状態を聞き、志大に働き、明治參十七年、時の本派本願寺執行武田篤初に謀りしに、氏は其擧を賛し後援を諾したれども巌氏は、唯身體の保護を求めしに止め資金の補助などは全然拒絶し、其代りに布敎については何等本願寺の指揮掣肘を受けないといふ事にして同年七月出發、釜山に上陸せられた、當時は日清戦争の初めで人心の同様甚だしかつたが、朝鮮の内地に入るには衣食住ともに鮮人ものに慣れなければならないと、翌日から朝鮮食をとつたと。
かくて巌氏は暫時して釜山より數里田舎にある、梵魚寺といふ大伽藍に行つた行くまでは、筆談で意志は通じる事と思つて居たが、行つて見ると、五六十人の僧侶中に筆談の出來るものは僅かに四五人にて、實に心細く感ぜられたが其内には少しづゝ朝鮮語を理解する様になり、また境内に物貰ひに來る子供などに、菓子を與へて書物を読ませて發音を覺えなどし、漸く意の通ずる様になり、同寺十ヶ月間滞在し後、江原道より全羅南道をかけて南韓半島を駆廻り、忠清南道全羅南道と西中部を或は雲水をやり、或は藥と菓子の行商などをして、再び釜山に歸り、通弁をやして資を得、また入船の時には積荷の上に寝明して夜番料を得夜は漢文などを勉強して生計を立てゝ居る内に領事の周旋にて、征韓の役に加藤清正が上陸したといふ温泉のある所へ、日韓語學校をたてる事にして行かれたが加藤清正に蹂躙された歴史のある所だけに、日本人に対しては好意を持たぬ、始は猜疑の眼を光らして仲々打ち解けなかつたが、領事とも相談して、氏は便利上、姓名も朝鮮人の如く李容明と変へたまた氏の父は韓人の漁夫で、近海漁業中暴風雨に遭遇して日本に漂流して、日本人に救助されて日本人の女との間に出來たのが、即ち氏といふ事に話したら、漸くなじむ様になり、成程朝鮮語の覺え方も早いなどとほめて、少々づゝ生徒も來る様になり、さゝやかなる韓人の家をかりて數人の生徒と起臥を共にしたが、彼地の習慣として食事は各自の家に歸り起臥は皆氏の家でする事になつて居る、
其後氏は愈々韓人布敎の途につき蔚山より慶州へ同じ處を四度も巡歴して、或は寺院に交渉しても借さず、或は街上に説法しても聴者は勿論、集まる人もなく、殆んど失望困憊して如何になり行くかと多少心細く感ぜられた時でも、南無阿弥陀佛の名號にまた勇氣を得て、撓まず布敎し居る内に、四度目に慶州に泊りし宿の主人に、此地に念佛信者は御座らぬかと尋ねたら、丁度其主人の兄が念佛信者で其人の奔走で同地の佛國寺といふに始め説敎らしい説敎をする事が出來て大に力を得、殊に慶州の地は吾國へ始めて佛敎を送りし所とて一層喜ばしく覺えられたとの事だ。
其後西本願寺の京城の説敎所を置くや其所の布敎に従事し、傍ら本願寺よりの留學生を指導せられたが、今は本願寺の方は後進に譲られて、自らは韓人監獄の敎誨師として鮮人間に布敎し居らるゝとの事である、目下の状況にては巌氏盡力の大聖敎會に属するもの、約二萬人して京城のものを本部として、各地に分敎會を置き、一敎會は大約五六十人位にて、分敎會の數は四十參、各分敎會の人々が夫々に月に一回位づゝ會合し、時には本部の方より行く事もあり、時には一枚刷の印刷物を配布したりして聯絡をとつて居る何分資金が不充分の爲め、布敎も思ふように任かせぬ事も多いとか。
また大聖敎會とは、耶蘇敎の敎會の様ですが、何か意味があるんですかと尋ねしに、始め布敎の時、本願寺などといひても鮮人には未だ知られず、已に外國宣敎師により敎會とか、聖とかいふ字は、多少宗敎的革新的意義のある文字として印象され居る故用ひたと云ふのであつた。